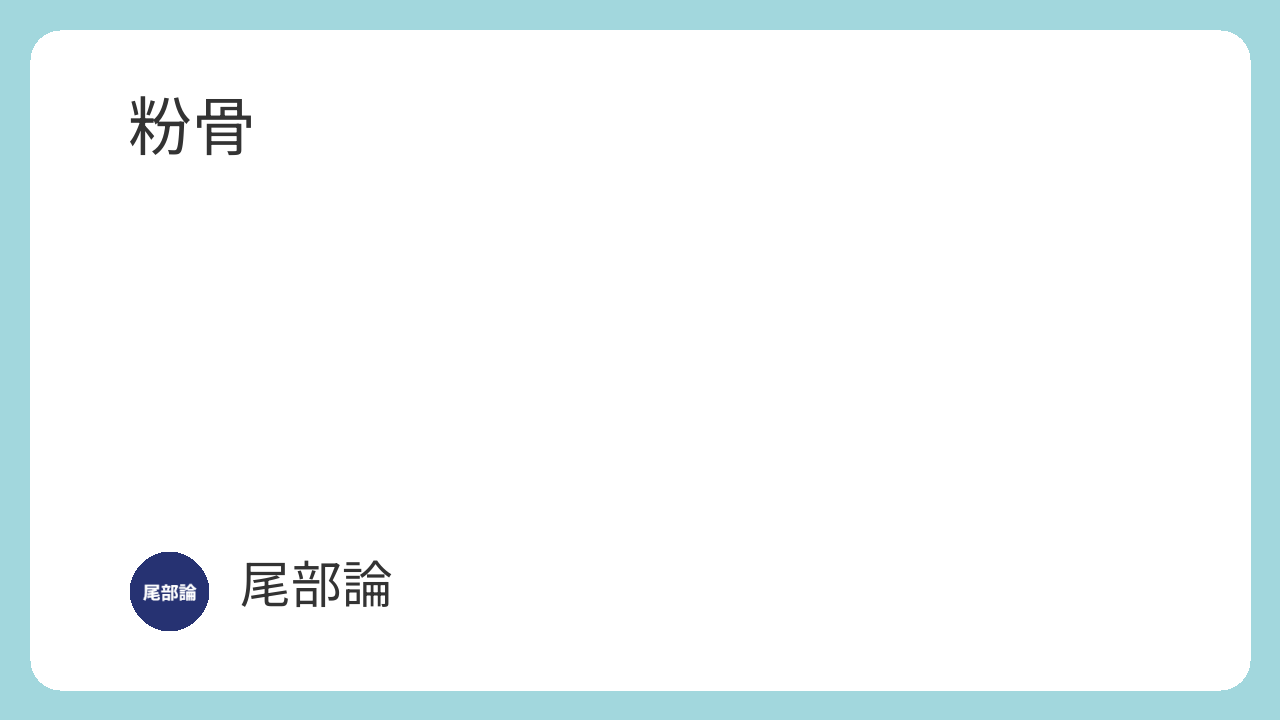古い時代の父親像で接して来た親父のスタンスが障壁となって下に組み敷かれ続けて育った息子の俺には、親父を死ぬまで愛せはしなかった。実際、見切りをつけて二十歳で家出して、俺は俺で我が道を進むことにした。ご挨拶程度に年2回程は顔を出したが、会う度に相変わらず上段の構えの親父に辟易した。その度毎、場を取り持つ為のお愛相だけ口にして早々に辞した。
一子長男なので世の当然としてその親父の骨を預かり、生前俺も資金を拠出した(若い頃俺にはカネの有った時期もあった)親父の故郷の秩父に建てた巨大な神道の奥都城には納骨せず、神道学者に相応しい出雲の海に散骨した。死の床で「どこに還りたいの?秩父それとも住んでた浦和?」という母の問い掛けに、どちらにも首合図で否定したらしく、小声で「い・ず・も」と答えたとのこと。IQの異常に高い母だから、この会話を態々俺に伝えたことには二つの打算があっただろう。まず、足腰が悪くなった母本人が好きでもない秩父の山奥に墓参するつもりが全くない事。二つ目は、仮に自分も「おとうちゃま」と一緒に納骨されるとして、俺にその遠い奥都城を守れるだけの経済力と意欲があるのか、という疑念。この話をしておけば、自責を負って墓を放棄しなくても、息子の俺がよしなに取り計らうだろう。嘘ではないし、出雲に散骨であれば親父に合ったストーリーにもなるし。大した母で、人には「おとうちゃまを息子が海に『捨てた』」と云っている。マイセン風の極小ミニ骨壺に一片だけおとうちゃまの骨を入れて渡したら、サ高住の自室のニトリの戸棚の上に小祭壇を作って祀って毎日おとうちゃまとお話ししている、そうである。
春先の出雲の海にしては波の穏やかな雲天日だったが、クルーザーに乗って散骨許可のある入江の先で漂泊した途端、大粒の雨が降り始めた。水溶性のビニール小袋に小分けされた親父の紛骨を海に投げ入れてゆく。音もなく、神官の祈祷もなく、黙々と海風の中へ投げ込んでゆく。悲しみもなく。日本の儀礼文化研究の泰斗と称されている親父らしいが著作を読んだこともない。型に妙に拘泥る儀礼を俺は型自体は極めれば美しいと思うことはあっても、型を振りかざす風習が嫌いだ。一切の儀礼を固辞して最も簡素なコースを選んだ。死んでしまえばそれまで。無だ。生きている間が全て。核家族化した日本で死者の墓を作っていけば、いずれ国土が墓で埋め尽されてしまう。海に還れ。あんたの研究していた古事記の頃に神々が渡って来た海だよ。
銅鑼が鳴り、竹籠に盛られた色とりどりの花びらを紛骨を投げ入れた辺りに撤く。儀式といえばこの略式版の散骨パッケージではこれだけだった。流石に可哀想に想って子供の頃習った二拝二拍手一拝(出雲大社では四拍らしいが…)黙礼をしていると、なる程良く考えたもので、浮んでいる花弁を目印にしてその周りを舟が周回し始めた。
「こんなに波が静かな日は珍しいんですよ。」
同乗した散骨業者が声を掛けて来た。東京から駆けつけて来たアンタがどうして知っているのかね、と思う。ただ、確かに海の畝は穏やかで舟は花びらの小さな群れのまわりを静かに弧を描いてゆっくりと漂航してゆく。舳先の俺には顔にかかる雨が不思議と気にならなかった。
おそらく親父に関する記憶が記録という量子の砂としてゼロポイント・フィールドに落とし込まれるまでに49日(中陰)なり50日(五十日祭)なり忌明けに至る他界後の一定の期間が必要で、要するにヒトの生命に宿っていた魂が抜けて拡散し、熱量を冷まして、その生命に記録されていた記憶を体温のない情報に濾過するプロセスが必ずあるのだろう。末達の魂が浮遊すれば怨念であれ夢であれ、その熱を感取する別のヒトの生命もこの期間、あっても不思議はない。
「俺はまだ死なねェヨ!」
入退院を繰り返していた時、一度だけ東京の俺のマンションで人の気配を感じて振り返ったら、アイランドキッチンの片側からスッと消え去る空気の塊があった。身の丈が丁度背の低い親父のようだった。そう言いに来た気がした。その夜、親父は持ち直した。魂が命から離れず、熱を取り戻したのだろう。
あとほぼ半年生きていれば親父は今日100歳となった。Outlookのカレンダーのリマインダーが知らせて来た。データを消去する。親父の生年月日の情報は時間のないゼロポイント・フィールドの量子となり、単体で意味を持たないものとなって全次元を浮遊してゆく。
せいせいするはずなのだが、そうでもない。手酷く毆打されていた嫌な記憶が薄れ、親父が単に不器用だったのではないかとも思うようにもなった。10人兄弟の末っ子として好き放題、愛され放題であった親父には、自分の愛情表現の学習機会が乏しかったのかもしれない。面映ゆいばかりであったかもしれない。今も許す気はないが、許すも許さないもない。親である記録は消去しようもない。
「あいつにはすまないことをした。」
そう母親に死の床で何回も言っていたと聞いた。